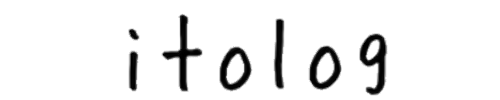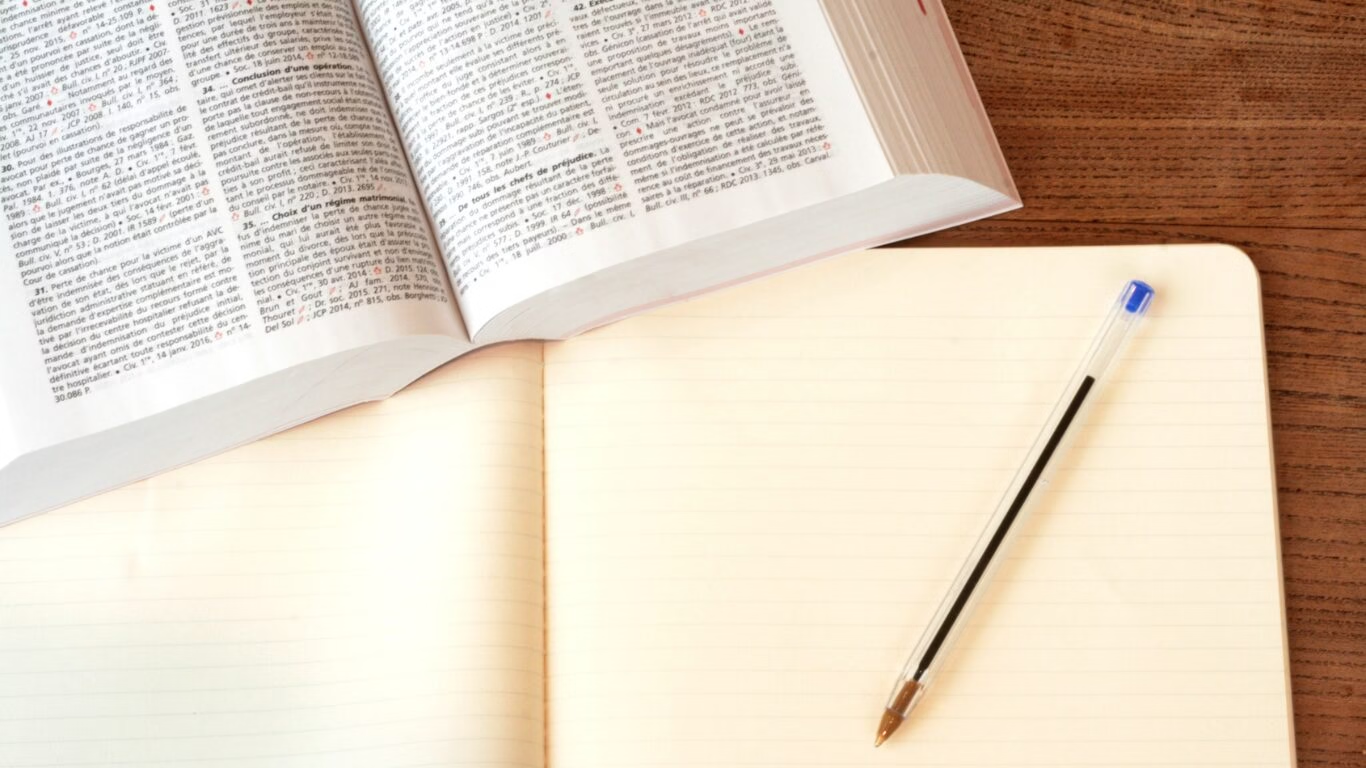はじめに
漢字検定(漢検)は、日本語の語彙力や読解力を向上させるのに役立つ資格です。特に2級・3級は、日常生活やビジネスでも活かせるレベルの知識が求められます。この記事では、私が独学で漢検3級と2級に合格した経験をもとに、独学で合格できるのか、効果的な勉強法やおすすめの教材、試験当日の注意点についてお伝えします。
漢検は独学で合格可能なのか
結論から申し上げますと十分合格可能です。
問題集を買って、しっかりと勉強すれば2級レベルまでは誰でも合格可能だと思います。
3級と2級の難易度の違い
3級:基礎的な漢字力を試すレベル
3級は中学校卒業程度のレベルで、基本的な常用漢字をしっかり押さえていれば合格できます。読めるけど書けない漢字もありますが、比較的馴染みのあるものが多いため、暗記すれば対応可能です。
詳しくは下の表をご覧ください。
レベル対象漢字数 中学校卒業程度(1623字) 主な出題内容
審査基準 程度
常用漢字のうち約1600字を理解し、文章の中で適切に使える。
領域・内容
《読むことと書くこと》
小学校学年別漢字配当表のすべての漢字と、その他の常用漢字約600字の読み書きを習得し、文章の中で適切に使える。
- 音読みと訓読みとを正しく理解していること
- 送り仮名や仮名遣いに注意して正しく書けること
- 熟語の構成を正しく理解していること
- 熟字訓、当て字を理解していること(乙女/おとめ、風邪/かぜ など)
- 対義語、類義語、同音・同訓異字を正しく理解していること
《四字熟語》
四字熟語を理解している。《部首》
部首を識別し、漢字の構成と意味を理解している。
2級:より高度な漢字知識が求められる
2級になると「読めるけど書けない」「知っているけど書けない」「そもそも知らない」という漢字が増えたように思います。特に四字熟語の範囲が広く、知らないものが多かったため、ここに時間をかけました。単に暗記するだけではなく、意味や成り立ちを理解することが重要です。
詳しい内容は下の表をご覧ください。
レベル対象漢字数 高校卒業・大学・一般程度(2136字)※常用漢字がすべて読み書き活用できるレベル 主な出題内容
審査基準 程度
すべての常用漢字を理解し、文章の中で適切に使える。
領域・内容
《読むことと書くこと》
すべての常用漢字の読み書きに習熟し、文章の中で適切に使える。
- 音読みと訓読みとを正しく理解していること
- 送り仮名や仮名遣いに注意して正しく書けること
- 熟語の構成を正しく理解していること
- 熟字訓、当て字を理解していること(海女/あま、玄人/くろうとなど)
- 対義語、類義語、同音・同訓異字などを正しく理解していること
《四字熟語》
典拠のある四字熟語を理解している(鶏口牛後、呉越同舟 など)。《部首》
部首を識別し、漢字の構成と意味を理解している。
効果的な勉強法
1. 反復学習を徹底する
漢字の勉強で最も大切なのは、繰り返し学習することです。一度覚えた漢字でも時間が経つと忘れてしまうため、定期的に復習する習慣をつけましょう。
2. 隙間時間を活用する
・学校の休み時間や移動時間を使って漢字の書き取りをする ・寝る前に軽く復習することで記憶を定着させる
3.声に出して覚える
紙などに「書く」という覚え方もいいのですが私のおすすめは声に出しながら覚えることです。
特に「読み」は声に出したほうが何倍も効果的です。
4. 四字熟語は意味ごとにグループ化する
2級で特に難しいと感じたのが四字熟語でした。無理に暗記するのではなく、
「勇猛果敢」「大胆不敵」→ 勇気に関するもの
「晴耕雨読」「温故知新」→ 生活や学問に関するもの など、意味ごとに分類すると覚えやすくなります。

またイメージで覚えるのもおすすめです。
たとえば、「勇猛果敢」でも、なんか勢いがある感じがする。くらいの認識でもいいので、自分なりの面白い覚え方で捉えると意外と覚えてしまえます。
4. モチベーションを維持する工夫
勉強が嫌になったときは、
- 思い切ってその日は休む
- 「今日はここまで」と小さな目標を設定する
- ご褒美(お菓子など)を用意する
無理に詰め込まず、楽しみながら学習を続けることが大切です。
おすすめの問題集・アプリ
私が実際に使っておすすめだと感じたものをご紹介します。
問題集

このシリーズが特に使いやすくおすすめです。
この教材は中学の時に漢検大好きの先生に教えてもらったものです。
実際にこの教材は問題カバー率が95%越えで、出る順になっていて、これを使ってテストを受けて、ほとんどこの教材に書かれていた問題が出たので効果は折り紙付きです。デメリットも特になく、頻出の問題を解くだけである程度の問題は解けるようになりますよ。
アプリ
スキマ時間の勉強に使える便利なアプリとして
『漢字検定・漢検漢字トレーニング』 というアプリがおすすめです。
リンクはこちらから
試験当日の様子と注意点
試験当日は若干ピリピリした雰囲気でした。私は学校で団体受験をしたため、試験会場が学校ということもあり、多少の安心感はありました。
注意点
- 試験は緊張する → 事前に過去問を解き、時間配分の感覚をつかんでおくことが大切。
- 試験は終わり次第退出可能 → これは意外でした。時間いっぱい使うか、見直しをしたら退出するかは自分次第です。
実際に漢検を取得して役立ったこと
漢検合格後、
- 読めなかった漢字が読めるようになった
- 本の理解力が向上した
- 語彙力が上がり、ブログの文章にも活かせるようになった
などのメリットを実感しました。漢字を学ぶことで、文章を読むスピードも上がり、より深く理解できるようになりました。
これから受験する人へのアドバイス
「漢検2級までは、しっかり勉強すれば誰でも合格できるレベル!」
実は、私は準2級に2回落ちています。しかし、「どうせ次受けるなら2級に挑戦しよう!」と思い、勉強を続けた結果、1発合格できたんです。
この経験から、「諦めずに挑戦することが大事」 だと学びました。また、「準2級よりも難しい2級を受けるんだから、しっかり勉強しないと!」という気持ちが、良いプレッシャーになったのも成功の要因です。
まとめ
・3級と2級では、特に四字熟語の難易度が大きく異なる
・効率よく勉強するには反復学習と隙間時間の活用が重要
・試験当日は緊張するが、事前準備をしっかりすれば大丈夫!
・漢検を取得すると語彙力や読解力が向上し、日常生活でも役立つ
・諦めずに挑戦し続ければ、合格できる!
これから受験する方も、ぜひ頑張ってください!